|
平成22年4月より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、国立・私立高校等の授業料に充てる高等学校等就学支援金を創設し、家庭の教育費負担が軽減されることになりました。高等学校等就学支援金の支給額は、月額9,900円(年額118,800円)で、保護者の所得によって、さらに加算される場合があり、最大で月額19,800円(年額237,600円)となります。今回、高等専修学校もその対象となり、私立高等学校と同等の扱いになりましたが、ここまで来るのに長い道のりがありました。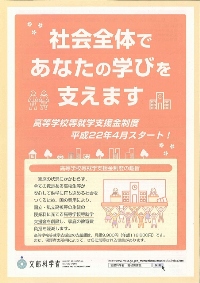
昭和60年、高等専修学校に「大学入学資格付与指定校」が認められ、昭和62年、国家公務員採用試験受験資格が認められました。また、平成5年、高等学校体育連盟主催大会への参加が認められ、平成6年、JR通学定期券割引が3年制の大学入学資格付与指定校に限り高等学校と同等になったのです。その後、平成16年、公共職業安定所の職業紹介業務の取扱が高等学校と同等になりました。
高等専修学校はわかりにくい学種故に「麻しんの予防接種」「耐震対応」「アスベスト対応」「AED導入対応」など生徒の命に関わる重要なことまでが忘れられていた事実もあり、また、「地上デジタル化対応」については最近になってやっと認められました。
今回、「高等学校等就学支援金」は高等学校と同等に扱って頂けましたが、「スポーツ振興センターへの加入格差」「経常費助成の格差」「高等学校野球連盟への加入格差」「都道府県の公私連絡協議会への参加格差」「公共施設利用料・入場料の格差」「社会福祉士介護福祉士学校指定格差」「衛生管理者認定格差」「激甚法格差」など依然としてその格差は存在し、1条校でないが故に、また、新たな格差が生まれているのです。国民に分かりやすい学校制度の確立と、この日本で学ぶ子ども達の将来を考えた高等専修学校の振興を願ってやみません。
|